目次
1.臓器の老化は20代から始まっています
2.検査からわかる臓器の健康度
3.臓器が老化してくると体にこんな変化が現れやすくなります
4.臓器を老化させる原因は「酸化」と「糖化」
5.臓器を守る3つの生活習慣
踏ん張りが利かなくなった、疲れが抜けにくくなった、根気が続かなくなったなど、体力が落ちてきただけと思っているかもしれませんが、実は全て臓器の老化によって起こる現象でもあります。人間は、生まれた瞬間から老い始めるもの。途中で逆戻しして、若返ることはできません。日々の「老い」を止めることはできませんが、老化のスピードを遅らせることはできます。
今回の記事では臓器が老化すると現れやすい変化や臓器を守る3つの生活習慣をお伝えします。ぜひ参考にしてください。
1.臓器の老化は20代から始まっています
階段を急いで駆け上がったとき、水たまりを飛び越えようとしたとき、「以前は、こんなことはなかったのに…」と、身体能力の衰えを感じることはないでしょうか。皮膚の潤いや張りが減ってきて、年齢を意識する人もいます。
こうした目に見える老化は誰でも実感できるものですが、目に見えない臓器も、20代をピークにその後は着実に衰え始めています。 ただし、見た目も人それぞれのように、臓器の老化にも大きな個人差が見られます。30代なのに50代より臓器の老化が進んでいる人もいます。臓器が老化するということは、元気で生きている時間、健康寿命がそれだけ短くなるということ。臓器の健康度こそ、あなたの健康寿命を決める大切な目安です。
2.検査からわかる臓器の健康度
臓器の健康度は、血液検査や腹部エコー検査から、予測できます。血液検査では主に動脈硬化による肉体の老化がどの程度進んでいるかを確認できます。全ての臓器に栄養や酸素を送り、老廃物を回収する血液。その通り道の血管を若く保つことが、臓器の若さと健康を維持する重要なカギです。
腹部エコー検査では、それぞれの臓器の大きさや、はれや腫瘍がないかなどを見ます。1cm以下の腫瘍でも発見でき、これは通常、血液検査では異常が見られず、自覚症状もないという段階です。なかなか病変に気づかない肝臓、膵臓などの異常も早期に発見できます。生涯にわたり、健やかな暮らしを快適に過ごすためにも、これらの検査が同時に受けられる人間ドックや健康診断を年に1度は受け、健康管理の指標にするのがおすすめです。
3.臓器が老化してくると体にこんな変化が現れやすくなります
脳血流量の低下により、活動に必要な酸素や栄養素が届きにくくなる→思考力やしゅちゅう集中力の低下に
・肝臓 解毒作用や栄養分の分解・合成・貯蔵などの機能が低下→脂肪肝から肝硬変にも
・膵臓 血糖を細胞に取り込むために必要なインスリンを作る力が低下する→血糖値が高い状態が続き、糖尿病に
・心臓 心臓の血管(冠動脈)の動脈硬化が進み、血液を引き込む力や押し出す力が弱くなる→運動時の息切れや動悸に
・腎臓 体に不必要な成分が排出されにくくなり、老廃物がたまりやすくなる→むくみや疲労感、血圧の上昇に
・胃腸 消化・吸収機能や排せつ機能が低下。腸内の悪玉菌が増えやすくなり免疫細胞の働きも低下→便秘や下痢の他、風邪やアレルギーを招きやすくなる
4.臓器を老化させる原因は「酸化」と「糖化」
「酸化」とは、一言で言うと「活性酸素」で体内の細胞が傷つけられることです。私たちが生きていくために不可欠な酸素ですが、その一部は体に有害な活性酸素に変化します。体には活性酸素の害から守るための酵素が備わっていますが、この酵素の働きは加齢とともに低下していきます。そのため、酸化した血中の悪玉コレステロールが血管をむしばんで、動脈硬化が一気に進んでしまう危険があります。
活性酸素の発生を抑えるには、活性酸素と戦う「抗酸化」の働きを持つ栄養素を積極的にとることがおすすめです。
抗酸化の作用が強い栄養素とそれらが多く含まれる食品は下記の通りです
・ビタミンC→オレンジやレモンなどのかんきつ類、カラーピーマン
・ビタミンE→あんきも、たらこ、モロヘイヤ
・アントシアニン→アサイー、ブルーベリー
・イソフラボン→大豆(納豆や豆腐などの大豆製品)
・セサミン→ごま
・リコピン→トマト、スイカ
「糖化」とは、たんぱく質と糖質が結びつく反応により、たんぱく質が劣化することです。人体のほとんどはたんぱく質からできていますから、臓器をつくるたんぱく質が劣化すると、老化に直結します。糖化で問題なのは、糖質のとりすぎです。ただし、糖質を排除する食生活は、健康被害の恐れもあります。
糖質の高い食べ物を食べると、血糖値(血液中のブドウ糖の数値)が上がります。そのときに血糖値が急上昇すると、体は「糖質のとりすぎ」と判断。体内で糖化が起こりやすくなるのです。そこで、血糖値を急上昇させない食事、つまり血糖値がゆるやかに上がるような食事の方法を取り入れることが大事になってきます。
血糖値の急上昇を抑える食事のポイントは下記の通りです。
GI値の低い食べ物を選ぶ
GI値というのは、血糖値が上昇する割合を数値化したものです。GI値が低いほど、血糖値の上昇はゆるやかということ。主食ならば「黒っぽいもののほうがGI値が低い」と覚えておくといいです。白いパンより全粒粉のパン、白米より玄米を選ぶとベターです。
野菜やキノコから食べる
おなかがすいているときに、いきなりご飯を食べれば、体は糖をグングン吸収します。すると血糖値は急上昇!先に野菜やキノコなど、食物繊維が多く含まれる食べ物を口に入れるよう心がけましょう。食物繊維には、糖質の吸収を抑え、血糖値の上昇をゆるやかにする働きがあるのです。
日常生活では、忍び寄る酸化と糖化から身を守るための意識と工夫が重要です。まずは下に挙げた3つの生活習慣から始めてみてください。
5.臓器を守る3つの生活習慣
脂肪と糖分を取りすぎない
・肉類(特に脂身)やバターなどの動物性脂肪や糖質を取りすぎない
・GI値の低い食べ物を選ぶ
・抗酸化作用のあるビタミンA/C/Eが含まれる緑黄色野菜・大豆食品などをしっかりとる
酸化ストレスを避ける
・過労や睡眠不足などの不摂生に注意し、ストレスは早めに解消する
・紫外線、排気ガス、電磁波など、活性酸素の生産を増やすものを避ける
食後にウォーキングをする
・食後の高血糖を防ぐ
・ストレス解消になり、酸化・糖化による動脈硬化の予防に役立つ
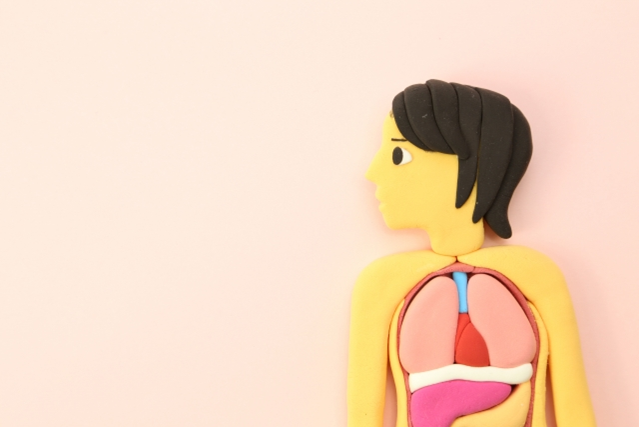


コメントを残す